これまでの頼山陽の史跡詩碑は『頼山陽史跡詩碑めぐり』にまとめています。
その後に見つかった、頼山陽ゆかりの場所を紹介するコーナーです。
2025・3・31
見延典子「脇黙斎と真光寺」
脇黙斎について書いたところ、再び青山さんから思いがけない話を知らされる。江戸後期に脇黙斎が屋敷があった地に、現在は真光寺という浄土真宗の寺が建っているというのである。


真光寺の前の通りは西国街道。JR山陽本線「西条駅」南口から徒歩9分。東広島市。
もともと真光寺は龍王山にあり、江戸期には現在地よりやや東にあったこという。現在地に移転したのは1875年(明治8)。3月29日付脇家が庄屋をつとめていた「西条東村」との位置関係や、西国街道に面していることから、ここに脇家があったという話の信憑性は高い。 続きます。
2025・3・29 見延典子「西条東村の脇黙斎、順庵父子」
江戸後期、西条四日市(東広島市)に暮らし、頼家の人々と親しく交流した人に庄屋の脇黙斎、順庵父子がいる。見延は、20年ほど前に頼山陽ネットワーク初代代表古川隆次郎さん(故人)と黙斎の墓を参ったことがある。
その話を青山浩子さんに話したところ、西条町誌に掲載の記事を送ってくださった。記載にある西条東村についてネットに以下の記載があった。
「西条東村は東広島市西条町西条東・西条西本町寺家村の東に位置する。竜王山から南流して黒瀬川に注ぐ半尾川を境に東の吉行村・四日市次郎丸村に接し、半尾川上流の飛郷行貞以外はすべて平地」
※「寺家」は西条の一つ広島寄りの駅名。1987年新設される。
西条駅北口徒歩10分にある安芸国分寺は「吉行」。

2025・3・26 見延典子 頼山陽の脱藩地点⑤
青山さんが西国街道の地図を送ってくださった。


地図を見ると「西条(四日市)」「白市」「田万里」「竹原」の位置関係がわかりやすい。これを見れば、山陽は田万里を回避して白市ルートを進んだことがわかる。松子山を田万里方面に下りたところにあった「日向一里塚」跡について「関所」と書いているネット上の地図がある。「関所」があるほかに
も、竹原が近づけば、顔見知りに会う可能性もあるだろう。
山陽自身、十代の終わりに本郷に近い仏通寺に逗留したことがある。知識として西国街道以外に白市ルートがあることくらいは知っていただろう。松子山の途中から「西条(四日市)」に戻ったというところに、計画性が感じられる。
但し、後に父春水がありのままを広島藩に報告したとは思えない。「心神狂妄の果てに出奔した」として藩主に嘆願する以上、計画性があったとは口が裂けても言えなかった。同時に春風や杏坪が知り得た山陽の脱藩の足取りも、万一を考えて、書き残すことはなかったと考えられる。
2025・3・25 見延典子
頼山陽の脱藩地点④
「記憶の上塗り」という言葉があるかどうかは知らないが、頼山陽を調べはじめてから、さまざまな情報が記憶にアップデートされていき、気がつけば最初にあった情報が変わってしまっていることがある。そこで「頼山陽の脱藩地点」についても、先達の本を読み返してみることにした。

見延は「頼山陽居室」について調べて以来、坂本箕山の業績はもう少し評価されるべきと考えている。なぜなら箕山は、山陽が顕彰されていく以前から山陽の研究を開始し、頼古梅や聿庵の妻千枝など頼宗家の人々と直接会って、「誇張されていない山陽」の話を聞き取っているからである。
右と下の記載は『頼山陽大観』から引き出したものである。山陽は松子山で家来の太助に「香典を忘れたから取りに帰れ」と命じ、断られると刀を抜いた。驚いた太助は竹原に走る。一方山陽は西条駅まで戻り、乞食と着物を交換し、白市方面を通って本郷へ向かったことなどが記されている。おそらく箕山は古梅や千枝から聞いた話をもとに書いているであろう。

「頼山陽の脱藩地点」を知っているのは、山陽自身と従者の家来太助だけである。太助は山陽が行方をくらました後、竹原の頼春風のもとに走り、事情を話した。その中には「頼山陽の脱藩地点」もあり、情報は山陽の行方を追うことになった石井豊州らや城下の頼杏坪と共有されたであろう。
見延が読み返したのは坂本箕山の『頼山陽』『頼山陽大観』である。タイトルこそ異なるが、内容が重複している頼山陽の研究本だ。


2025・3・24
見延典子
頼山陽の和歌に「松子山」
いっしょに松子山を「下山」した青山浩子さんから、頼山陽の詠んだ和歌に「松子山」の語が入って和歌があることを教えていただく。

憶母和歌
花もみせつもみちも見せつ
我母につかれて帰る
雪ふらぬ間に
松子山まつ子はあれと
かさなれる
は山しけ山
こゑそわつらふ
山陽が詠み、書いた和歌の原本は杉ノ木資料に収蔵されているそうだ。


ところで、青山さんは「頼山陽が母と松子山(西国街道)を歩いているときに堂々と松子山について詠んでいることから、松子山は脱藩地点ではないのではないか」とおっしゃっていた。
そうだろうか? 「松子山まつ子はあれとかさなれる は山しけ山こゑそわつらふ」の和歌にある「端山茂山」は木の葉が茂ることから「人目が多い」の意味。「まつ子」はそのままでは「母を待つ子」となろうが、漢文で書けば「待子」つまり「母が子を待つ」という意味になる。
そこで見延の意訳は以下の通り
今、母上とともに松子山にさしかかりました。脱藩の後、母上が帰りを待った子(山陽)はここにおりますが、多くの人々が今もその話を持ち出して、なんと煩わしいことでしょう。
青山さん、いかがでしょうか?

道が途切れ、目の前が開け、見えてきたのは「日向一里塚」。説明板が立っていたけれども、無事に下ることができた安堵感から、読もうという気にはならない。西本さんはもちろん尾崎代表、青山さんも晴れやかな表情だ。
2025・3・22 見延典子
「頼山陽の脱藩地点を求めて」③
松子山峠から下りはじめて45分くらいたったころ、車が行き交う音が聞こえはじめた。

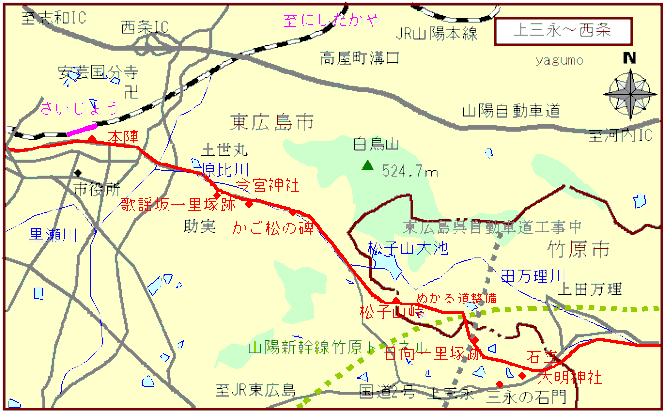


乾杯し、談笑していると、雨が降り出してきた。ホントの話である。
少々休憩して、そのまま旧山陽道を竹原方面へ進む。西本さんは田万里まで歩きたそうであったが、風がつよくなり、雲行きがあやしくなってきたので、西条方面までも戻ることに。

バスとタクシーをのりづき、入ったのは昼飲みのできる店(笑)

2025・3・20 見延典子
「頼山陽の脱藩地点を求めて」②
いきなり現れた「旧山陽道松子山峠」の石碑。というわけで、松子山に登るはずが、松子山を田万里(竹原市)方面に下山していくことになった。


引率をお願いした西本さん(右端)は3年ぶりの松子山という。ときどき地図を確認しつつ進む。

頼山陽、頼一族はもちろん、江戸時代は旅人が往来した道である。


「ぬかるみがあるかも」という事前情報のように地面は湿っぽい。


数日間降り続いた雨のせいもあって、池の水位も上がっているようだ。通常なら路面が見えているところにまで水が流れこんでいるので、渡れそうなルートを見つけつつ進む。
2025・3・19 見延典子「頼山陽の脱藩地点を求めて」①
第2回頼山陽ウォークは頼山陽の脱藩地点を求めて、松子山(東広島市~竹原市)に登ろうと考えて下見に出かける。

目指したのは西条駅からタクシーで10分ほどのところにある4年前にできたゴミ処理施設「広島中央エコパーク」。このそばを西国街道が走っており、東へ行けば竹原、西へ行けば西条(江戸時代は四日市と呼ばれた)。上の写真「広島中央エコパーク」の建物の後方がその辺りである。
頼山陽が脱藩した地点ははっきりしないが、通説として松子山峠付近ではないかといわれている(要検証)
今回はその松子山の峠越えをするため、案内人に地元の西本さんをお願いし、尾崎代表、青山さん、見延が登山に挑もうとしたのであったが、なんと、歩きはじめてわずか1分で「旧山陽道(西国街道)松子山峠」の石碑が立っているではないか。え? 余りの出来事に唖然とする。



春水二男大二郎の墓は、片面写真上「頼惟完二男」写真右「寛政八年丙辰五月二七日〇」
彼岸前の清掃をかね、今回は墓の背面、側面の撮影をする。


2025・3・16
石村良子相談役
「古文書研究会課外研修」
3月13日は頼山陽史跡資料館、古文書研究会の多聞院頼家の墓所課外研修。
先ずは『頼山陽詩碑歌碑めぐり』で予習を済ませる。

同年五月六日より高砂菅野仲右衛門頼家逗留、九日大二郎発熱、二十七日死亡、六月十四日久太郎宿痾暴発、六月二十八日仲衛門出立の申し出。この間仲衛門の心境は如何?

楠公追慕塔の入り口門柱を調べる。
昭和14年末裔楠正彦とある。末裔は木なし。
「古文書研究会」は毎月2.4木曜日14時から16時。次回より頼山陽脱藩の年、寛政12年の「春水日記」、訳本を参考にしながら原本を読みます。当時の武士の実態は日記ならではの面白さです。 お仲間を募集しております。
